家屋調査の費用はいくら?相場・内訳・安くする方法を徹底解説
「家を解体することになったけど、“家屋調査”って本当に必要なの? それに費用ってどれくらいかかるの…?」
そんな疑問や不安を抱えていませんか?
家屋調査は、建物の構造や老朽状況、隣家との距離などを調べて、安全かつトラブルなく解体工事を進めるための大切な準備です。
とはいえ、あまり馴染みのない調査だけに、「どんなことをするの?」「費用は?」と不安に感じる方も少なくありません。この記事では、家屋調査の費用目安やポイントをわかりやすく解説します。
ぜひ参考にして、安心して解体工事を進めてください。
家屋調査とは?必要な理由と目的

家屋調査とは、建物の状態を正確に記録・把握するための専門的な調査です。
主に解体工事や隣接工事の前後に行われ、建物の既存の損傷や工事による影響を確認するために実施されます。
解体工事前に家屋調査を行う理由
たとえば、Aさんが住宅を解体する際、隣のBさんの家に小さなヒビや傾きがあったとします。
事前に確認せず工事を進めると、解体後にBさんが「工事が原因だ」と主張する可能性があります。
これは思わぬトラブルや損害賠償請求につながるおそれがあります。
そのため、家屋調査ではあらかじめ建物の状態を記録しておくことが重要です。
調査は法律で義務付けられているわけではありませんが、安全かつ円滑に工事を進める準備工程として不可欠です。
家屋調査で確認される主なポイント
- 家屋の全景写真
- 建具(ドア・窓など)の建て付け状態
- 基礎や内装のひび割れ
- 外壁のクラックや雨漏りの有無
- 瓦のズレや割れ
- 建物や地盤の水平状態
- 地盤の高さや沈下状況
- 土間コンクリートのひび割れ
- 塀の破損状況 など
これらの情報を事前に写真や測定結果として残すことで、「解体工事前からあった損傷か、工事後に起きたものか」が明確になり、近隣とのトラブル防止につながります。
家屋調査でトラブルを回避する具体策
- 調査前に近隣住民への事前説明や挨拶を行う
- 調査結果を写真や測定データとして報告書に残す
- 記録した損傷箇所を保険申請やトラブル対応に活用
- 立会い可能なら、自分も現場に同席して状態を確認
誰が家屋調査を行うのか
調査は、民間の調査会社、建築士、不動産業者などが実施します。

家屋調査の費用相場は?3~10万円が目安
家屋調査にかかる費用は、おおよそ3万円から10万円程度が一般的な相場です。
費用に影響する5つのポイント
家屋調査の費用は、調査対象の建物の種類や規模、調査内容、現場の状況などによって変わります。
ここでは、費用に特に影響が大きい5つのポイントを詳しくご紹介します。
①建物の大きさ
建物が大きいほど調査範囲が広くなるため、費用は高くなる傾向があります。
たとえば、平屋の木造住宅と比べ、複数階建ての鉄筋コンクリート造の建物は調査に手間がかかるため、費用も高めです。
②建物の種類
住宅とビル・マンションでは調査内容が異なります。
マンションやビルの場合、共用部分だけを調査するケースもあり、その場合は費用を抑えられます。
具体的には、階段やエントランスなど共有部分だけを対象に調査する方法です。
③調査項目の数
調査内容や項目が多いほど、費用は高くなります。
たとえば、隣接する複数の建物を同時に調べたり、近隣住民への聞き取り調査が必要な場合は、手間が増えるため費用も上がりやすくなります。
④一度に依頼する建物の数
複数の建物をまとめて依頼すると、調査員の移動時間が効率化され、1軒あたりの費用を抑えられることがあります。
複数物件を同時に依頼するのは、費用を節約するうえで有効な方法です。
⑤調査現場までの距離
調査会社の拠点から現場までの距離が遠い場合、交通費や移動時間がかかるため、費用が高くなる傾向があります。
- 複数物件をまとめて依頼
- 図面や建物情報を事前に準備
- 調査項目を必要最小限に絞る
家屋調査を依頼する前の準備
家屋調査をスムーズに進めるためには、事前準備が大切です。
持ち物リスト
調査当日に必ず用意しておきたい持ち物です。
- 建築図面・設計図
- 建物の構造や間取り、増改築の履歴が分かる図面は、調査員の作業効率を大幅にアップさせます。
- 古い建物で図面がない場合は、手書きの間取り図や過去の写真でも代用可能です。
- 建物の鍵
- 調査員が建物内部を確認できるように、玄関・門扉・倉庫などの鍵を準備します。
- 印鑑・本人確認書類
- 契約や受領書へのサインが必要になることがあります。
- 建物情報メモ
- 築年数や増改築履歴、以前の損傷や補修箇所の記録などをまとめておくと、調査員への説明がスムーズです。
調査員に事前に伝えるべき情報
調査の精度を高めるためには、事前に以下の情報を伝えると良いです。
- 建物の種類
- 戸建て・集合住宅・木造・鉄筋コンクリート造など、構造や種類によって調査内容や費用が変わります。
- 築年数・構造の特徴
- 築年数が古い建物や、増改築を重ねた建物は調査に時間がかかる場合があります。
- 解体予定時期や目的
- 解体前、新築、売却、補助金申請など目的を明確に伝えることで、調査員が報告書に反映すべきポイントを優先的に確認できます。
- 過去の損傷やトラブル情報
- 既存のひび割れ、雨漏り、傾きなどの記録がある場合は、事前に共有しておくと報告書の精度が上がります。
立会いの有無を確認する
- 可能であれば、依頼者自身も立ち会うことをおすすめします。
- 立会いすることで、損傷箇所や不明点をその場で確認でき、報告書に反映される情報の正確性が高まります。
- 立会いが難しい場合は、写真や動画で事前に状況を伝える方法もあります。
家屋調査の流れと依頼方法
① 調査会社を選ぶ
まずは、家屋調査を実施している会社に連絡し、費用や対応内容を確認しましょう。
調査内容や建物の規模によって費用は変わるため、事前に見積りを取ることが重要です。
また、報告書の有無や対応エリアも確認しておくと、安心して依頼できます。
- 調査予定の建物の所在地
- 建物の種類(戸建て・木造・空き家など)
- 解体の予定時期や理由(解体前・新築のためなど)
② 図面の準備(可能な場合)
建物の図面があれば、事前に用意して調査会社に共有するとスムーズです。
古い建物や図面がない場合でも、調査会社が現地で対応してくれることが多いため、安心して依頼できます。
③ 現地調査の実施
調査当日は、調査員が現地に訪れ、以下のような項目をチェックします:
- 建物の外観、基礎、壁面、屋根の状態
- 隣接地との関係性や安全確認
- 必要に応じてレーザー測定器や水平器による精密測定
住宅密集地では、近隣住民への説明や挨拶が必要になる場合もあります。
調査会社が代行するケースも多いため、事前に確認しておくと安心です。
④ 調査報告書の受け取り
調査完了後、調査結果をまとめた報告書が発行されます。
報告書には、以下の情報が記載されます:
- 建物の写真や図面
- ひび割れ箇所や建物の傾き
- 近隣トラブル防止のための状態確認
報告書は保険申請やトラブル対応の証拠資料としても重要です。大切に保管しましょう。
関連情報・参考コンテンツ
家屋調査を終えたら、次のステップを知ることで、解体や売却の手続きをさらにスムーズに進められます。
以下の記事もあわせてチェックしてみてください。
- 解体工事の流れ
家屋調査の結果をもとに、解体工事がどのように進むのかをステップごとに解説。準備から完工までの流れを理解することで、トラブルを防ぎやすくなります。 - 古家付きと更地売却の違い・メリット比較
空き家や古家を売却する際の注意点やメリットを比較。家屋調査を活用して、正確な物件評価が可能になります。 - 家の解体費用
解体費用の目安や節約ポイントを確認できます。複数業者の見積り比較にも役立ちます。

都道府県別に解体工事会社と解体費用相場を見る
-
北海道・東北
-
関東
-
甲信越・北陸
-
東海
-
関西
-
中国
-
四国
-
九州・沖縄





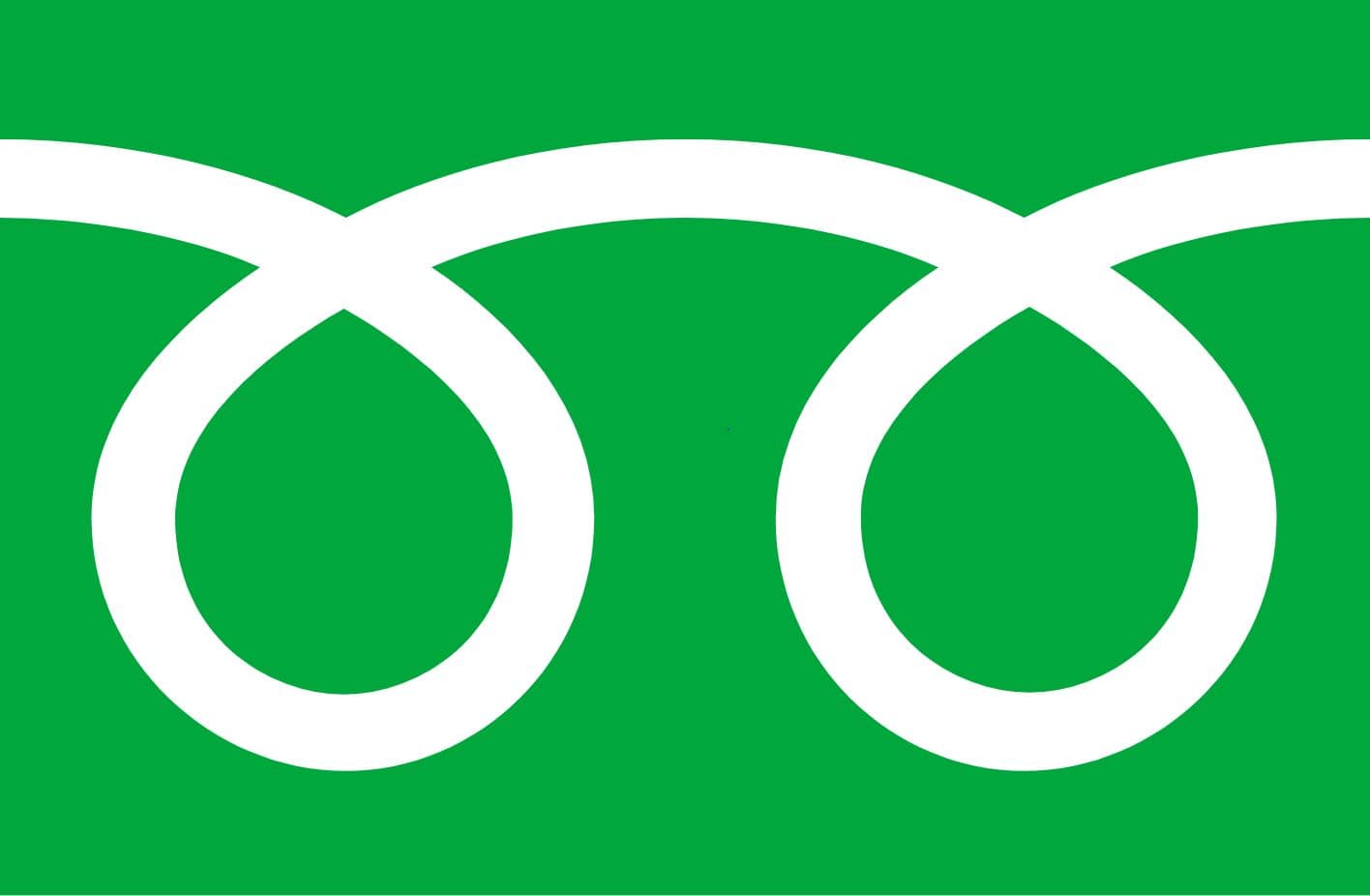 0120-479-033
0120-479-033