アスベスト除去の完全ガイド|費用・方法・飛散レベル・必要資格まで徹底解説
アスベストは、かつて建築資材として広く使用されていましたが、健康被害のリスクがあることから、現在では除去が義務付けられています。しかし、アスベスト除去には高額な費用がかかることもあり、具体的な相場や工事の進め方について不安を抱える方も多いのではないでしょうか?
本記事では、アスベスト除去の除去方法、費用相場、補助金制度について解説します。適切な対策を講じることで、安全かつコストを抑えたアスベスト除去を進めることができますので、ぜひ参考にしてください。
アスベスト(石綿)とは?
アスベストは天然に産出される鉱物で、「石綿(いしわた/せきめん)」とも呼ばれています。
現在の日本では、アスベストの製造や使用は法律で禁止されています。しかし、かつては建築材料として広く使用されていたため、現在でもアスベストを含む建築物が多く残存している状況です。
また、アスベストはその「発じん性」(粉じんが発生しやすい性質)によって、レベル1、レベル2、レベル3の3つに分類されています。
発じん性が高いほど、解体作業時の飛散リスクも高まるため、より厳しい管理が求められます。
レベル1: 発じん性が最も高く、飛散しやすい。
レベル2: 中程度の発じん性。
レベル3: 発じん性が比較的低い。
アスベストの除去方法は?
アスベストの除去方法には、主に3つの工法があります。それぞれの工法は、アスベストをどのように取り扱うか、また飛散を防ぐためにどのような処置が施されるかに大きな違いがあります。
| 除去工法 | 封じ込め工法 | 囲い込み工法 |
 |  |  |
| 吹付アスベストを下地から取り除く方法。アスベスト含有建材が完全に除去されるので、最も確実で安全な工法 | 吹付アスベストの層を残したまま、薬剤等を含浸したり、造膜材を散布し、アスベストを固定することで飛散を防止する工法 建物の取り壊し時には、除去工事が必要になる。 | 吹付アスベスト等の層を残したまま、板状材料等で覆う事で、粉塵の飛散や損傷防止を図る工法 建物の取り壊し時には、除去工事が必要になる。 |
アスベスト除去の費用相場
解体工事を行う建物にアスベストが含まれている場合、事前にアスベスト除去工事を行う必要があります。アスベスト除去費用は、処理面積とアスベストの発じん性(飛散性)によって異なります。
アスベスト除去費用の目安
処理面積による費用目安は以下の通りです。
| 処理面積 | 費用の目安 |
|---|---|
| 300㎡未満 | 2万~8.5万円/㎡ |
| 300㎡~1,000㎡ | 1.5万~4.5万円/㎡ |
| 1,000㎡以上 | 1万~3万円/㎡ |
※上記の費用には、事前調査、仮設工事、廃棄物処理など、除去工事に関連するすべての費用が含まれます。
例えば、処理面積が100㎡の場合、200万円~600万円の費用がかかる計算となります。ただし、処理面積は建物の延床面積と異なるため、事前調査を行って実際に除去が必要な範囲を確認することが重要です。
またアスベストは発じん性(飛散性)によって3つのレベルに分類され、発じん性が高いほど除去工事が難しく、費用も高くなります。

アスベスト除去に関する補助金
アスベスト除去工事には、補助金制度が適用される場合があります。これらの補助金は、特定の地方公共団体を通じて申請することができ、対象となる地域や条件に応じて、工事費用の一部を補助してもらうことが可能です。
アスベスト除去費用に対する補助金
アスベスト除去費用に対する補助金は、アスベストを含む建材の安全な除去工事費用を支援する制度です。除去工事は高度な技術と厳格な安全管理が必要なため、通常の解体工事より費用が高額になることが一般的です。通常、事前にアスベスト調査を行い、その結果に基づいて除去が必要と認められた場合に補助金が適用されます。
補助金を提供している自治体では、アスベスト除去費用の一部を支給しています。金額や上限額は自治体によって異なるため、申請前に最新情報を確認することが重要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象のアスベスト | 吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウール |
| 対象建築物 | 吹付けアスベスト等が施工されている住宅・建築物 |
| 補助内容 | 対象建築物の所有者等が行う吹付けアスベスト等の除去、封じ込めまたは囲い込みに要する費用(建築物の解体・除去を行う場合にあってはアスベスト除去に要する費用相当分) |
またアスベストの除去だけではなく、アスベスト調査費用に対して使える補助金もあります。
アスベスト調査・除去に必要な資格とは?
アスベストは、適切に除去しなければ周辺住民の健康に深刻な影響を及ぼす可能性があります。そのため、アスベスト除去工事を行うには、高度な専門知識と技術が必要です。また、アスベストが含まれているかどうかを事前に確認するため、アスベスト調査が義務付けられています。
【アスベスト調査とは?】
アスベスト調査では、設計図書の確認や現場の目視調査を行い、使用されている建材が設計図と一致しているかを確認します。この調査結果は、現場に掲示するとともに、3年間の保存義務があります。
①石綿含有建材調査者
2023年10月1日から、この資格を持つ者だけがアスベストの事前調査を行うことができます。建築物の解体・改修工事を行う前に、石綿含有建材調査者の資格を持つ者がアスベストの有無を確認することが義務付けられています。
資格取得の条件
石綿含有建材調査者の資格を取得するには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
- 石綿作業主任者の資格がある
- 大学の建築・またはそれに関連する課程を卒業した後、建築に関して二年以上の実務の経験がある
- 建築に関する短期大学※1を卒業した後、建築に関して3年以上の実務の経験を有する者
- 建築に関する短期大学、又は高等専門学校を卒業し、建築に関して4年以上の実務の経験がある
- 建築に関する課程の高校、または中学校を卒業した後、建築に関して7年以上の実務の経験がある
- 建築に関して11年以上の実務の経験がある
- 特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した上で、建築物石綿含有建材調査に関して五年以上の実務の経験がある
- 建築行政に関して二年以上の実務の経験がある
- 石綿の飛散の防止に関するものに限り、環境行政に関して二年以上の実務の経験がある
- 産業安全専門官・労働衛生専門官・産業安全専門官・労働衛生専門官のいずれかの経験がある
- 労働基準監督官として二年以上その職務の経験がある
- 2~11のいずれかと同等以上の知識及び経験を有する者
② 石綿作業主任者
アスベストを含む現場では、石綿作業主任者を1人以上選任することが義務付けられています。この資格は、現場での作業管理や安全対策の監督を行う際に必要で、法令を遵守しながら作業を円滑に進めるリーダー的な役割を担います。
資格取得方法
石綿作業主任者の資格を取得するには、石綿作業主任者技能講習を受講し、修了試験に合格する必要があります。講習は約10時間にわたり実施され、試験に合格する必要があります。
③ 石綿取扱作業従事者
実際にアスベストの除去作業を行うためには、石綿取扱作業従事者の資格が必要です。現場での手作業や除去作業に直接関与する作業員向けの資格で、適切な安全対策を実施しながら作業を行うことが求められます。
資格取得方法
この資格を取得するには、石綿取扱作業従事者特別教育を受講する必要があります。合計4.5時間の講習で、石綿の有害性や安全対策について学びます。
④ 2023年9月30日までに日本アスベスト調査診断協会に登録されている者
2023年9月30日以前に、日本アスベスト調査診断協会に登録されている者は、アスベスト調査・除去を実施することが可能です。
まとめ
アスベスト除去費用について、相場や工事内容、補助金制度についてご紹介しました。アスベストは1975年に規制が始まり、2006年には全面的に禁止されていますが、1955年から1975年に建てられた建物では、アスベストが多く使用されていました。
特にこの時期に建てられた建物を解体する場合、アスベストの有無を設計図書などで確認し、解体費用が高額になる可能性を理解しておくことが重要です。しかし、自治体によっては補助金制度を利用できる場合もありますので、ぜひ活用を検討しましょう。
アスベスト除去工事を実施する際は、専門知識を持つ業者を選ぶことや、事前調査を徹底することが求められます。この記事で紹介した情報を参考に、慎重に検討し、適切な工事を進めてください。

都道府県別に解体工事会社と解体費用相場を見る
-
北海道・東北
-
関東
-
甲信越・北陸
-
東海
-
関西
-
中国
-
四国
-
九州・沖縄




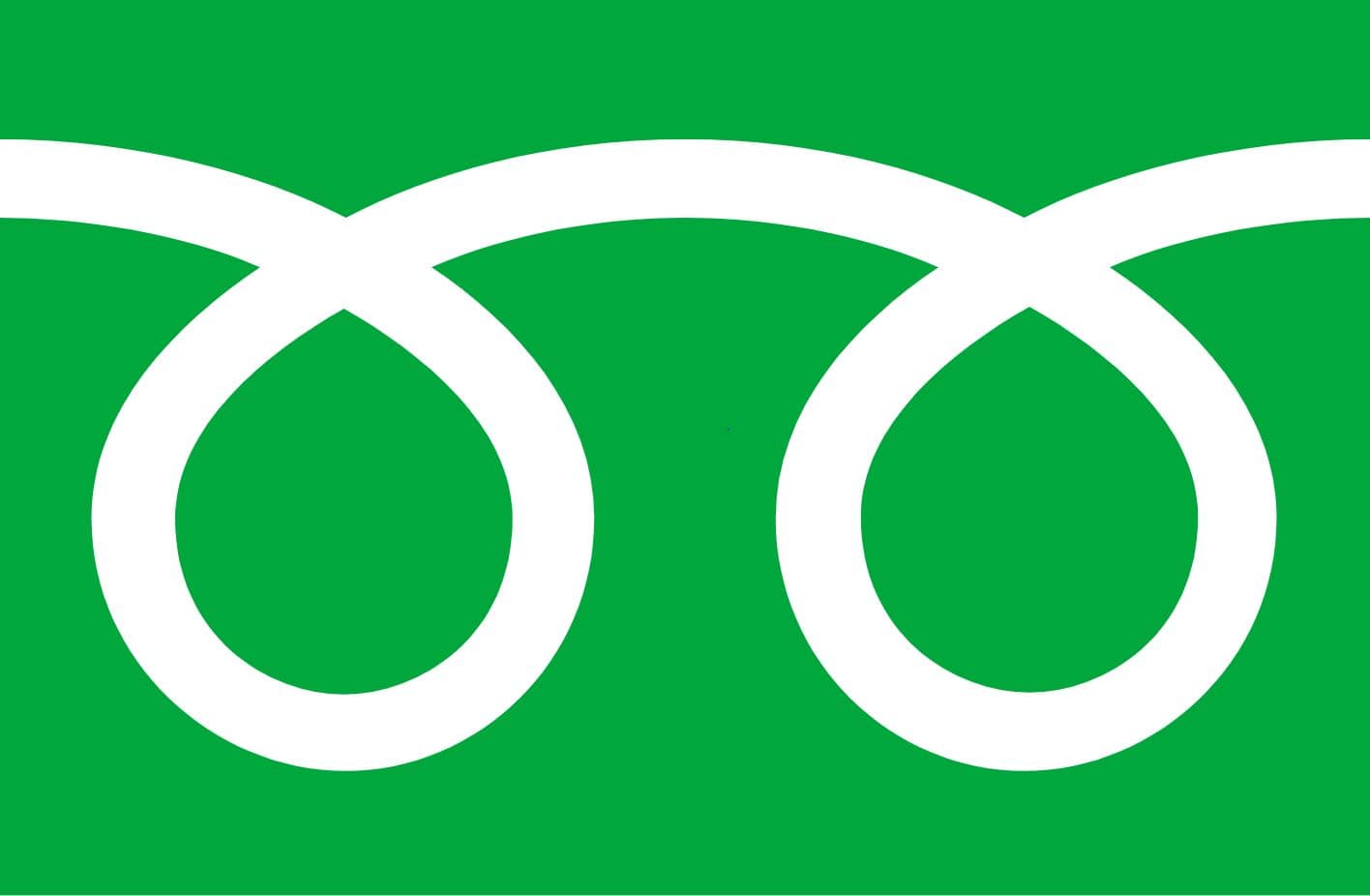 0120-479-033
0120-479-033