家を自分で解体できる?解体の流れ・必要な手続き・注意点を徹底解説
「家の解体を自分でできるのか?」と考えている方も多いのではないでしょうか。結論からいうと、家の解体は自分で行うことが可能です。
本記事では、自分で家を解体しようと考えている方に向けて、必要な費用や手続き、解体の流れや注意点を詳しく解説します。「解体費用を少しでも抑えたい」「業者に頼まず自分で進める方法を知りたい」という方は、ぜひ参考にしてください。
目次
- 家を自分で解体することはできる?
- 家を自分で解体をするときの流れ
- 家を自分で解体する際に必要な申請と手続き
- 家を自分で解体したら費用はいくらになる?
- 家を自分で解体するメリット・デメリット
- 家を自分で解体工事を行う際の注意点
- まとめ
家を自分で解体することはできる?

自分の家を解体することは可能です。通常、解体工事を行う際には「建設業許可」や「解体工事業登録」が必要ですが、これらはあくまで事業として解体工事を行う場合に必要な許可です。
自分で解体作業を行う場合、特別な許可を取得する必要はありません。
- レベル1・レベル2のアスベストは専門の許可を持つ業者でなければ撤去できません。無許可での作業は法律違反となるため、必ず専門業者に依頼しましょう。
- 解体工事で重機や工事車両を運転するには車両系建設機械運転者の免許が必要です。無資格での操作は違反となるため、事前に確認が必要です。
家を自分で解体をするときの流れ
自分で家を解体する際は、適切な手順を踏むことが重要です。計画的に進めないと、思わぬトラブルや危険が伴うため、各工程をしっかり把握しておきましょう。以下のステップに沿って、安全かつスムーズに作業を進めていきましょう。
-
ステップ1
事前準備と計画
解体工事をスムーズに進めるために、まずはしっかりと準備を行いましょう。事前の手続きや近隣への配慮を怠ると、トラブルの原因になることもあるため注意が必要です。
- 自治体への届出
建設リサイクル法に基づき、延床面積80㎡以上の建物を解体する場合は届出が必要です。
- ライフラインの停止・撤去
電気・ガス・水道・電話の契約を解約し、撤去手続きを済ませる必要があります。
- 近隣住民への挨拶
解体工事では騒音や粉じんが発生するため、トラブルを防ぐためにも事前に近隣住民への挨拶を行い、説明しておくことが大切です。
- 自治体への届出
-
ステップ2
内装の撤去
準備が整ったら、建物の内部から順番に解体を進めます。まずは室内に残っている家具や家電を処分し、スペースを確保します。使えるものはリサイクルショップや自治体の回収を利用すると、処分費用を抑えられることもあります。
次に、壁紙や畳の撤去を行います。壁紙は剥がしやすい場所からゆっくりとはがし、畳は一枚ずつ運び出していきます。
さらに、窓ガラスやドアの取り外しを進めます。窓ガラスは割れないよう慎重に作業し、怪我をしないように軍手や保護具を着用しておくと安全です。ドアや建具も一つずつ取り外し、搬出の準備を整えます。
-
ステップ3
屋根や外壁の解体
本格的な解体作業に入ります。まずは屋根材を撤去し、建物の骨組みを解体しやすくすることが重要です。トタンや瓦を外し、落下や飛散に注意しながら慎重に作業を進めます。次に、外壁や柱を取り壊します。ハンマーや電動工具を使いながら、建物の構造を考慮しつつ安全に解体を進めていきます。
-
ステップ4
土台・基礎の撤去
屋根や外壁を取り除いたら、次は家の土台や基礎部分の解体を行います。床材を剥がし、建物を支えていた基礎コンクリートを砕いて撤去する作業が発生します。コンクリートの解体には専門的な道具が必要なため、作業を行う際は十分な準備と安全対策が欠かせません。
-
ステップ5
廃材の処理
解体工事が進むにつれて、大量の廃材が発生します。これらは適切に分別し、法律に則って処分しなければなりません。木材や金属、コンクリートなどの素材ごとに仕分けを行い、産業廃棄物処理業者に回収を依頼するのが一般的です。不法投棄は厳しい罰則が科されるため、正しい処理を徹底することが重要です。
-
ステップ6
整地作業
屋根や外壁を取り除いたら、次は家の土台や基礎部分の解体を行います。床材を剥がし、建物を支えていた基礎コンクリートを砕いて撤去する作業が発生します。コンクリートの解体には専門的な道具が必要なため、作業を行う際は十分な準備と安全対策が欠かせません。
家を自分で解体する際に必要な申請と手続き
工事前に必要な申請・手続き
- 建設リサイクル法に基づく事前申請(床面積80㎡以上)
「建設リサイクル法」により、床面積80㎡以上の建物を解体する際には、自治体への届出が義務付けられています。
申請は工事開始の7日前までに行う必要があり、届出を怠ると罰則が科されることもあります。
- ライフラインの停止手続き(電気・ガス・電話)
解体工事を行う前に、電気・ガス・電話などのライフラインを停止・撤去する手続きを行う必要があります。
※もし粉塵対策のため、散水をする場合は水道は止めないようにしましょう。
- 道路占用許可(工事中に道路に車両を停車させる場合)
工事中に道路上にトラックや重機を駐車する場合は、警察署の許可が必要です。
- 近隣住民への説明(騒音・粉じん・安全対策)
解体工事は、騒音・振動・粉じんが発生するため、近隣住民への説明を事前に行うことが重要です。
- その他、地域の法律や条例に基づく申請
自治体ごとに独自の条例や手続きが必要な場合があります。特に、景観地区や歴史的建造物がある地域では、解体に関する追加の手続きが必要になることがあります。
工事後に必要な申請・手続き
- 建物滅失登記(解体後1カ月以内)
建物を解体した後、法務局に「建物滅失登記」を行う必要があります。
これを怠ると、固定資産税がそのまま課税され続けるため注意が必要です。
- マニフェスト伝票の回収(廃棄物処理に関する書類)
解体工事で発生した廃棄物は、適切に処理されたことを証明する「マニフェスト伝票」を受け取る必要があります。
- 近隣への御礼(トラブル防止と良好な関係維持)
解体工事後は、近隣住民へ「工事が無事完了したことの報告」と「協力への感謝」を伝えると良い印象を持たれます。
家を自分で解体したら費用はいくらになる?
家を自分で解体する場合、業者に依頼するよりも費用を30~50%削減できる可能性があります。しかし、解体には道具の購入・レンタル、廃材処分費など、さまざまな費用がかかるため、事前にしっかりと見積もりを立てることが重要です。
自分で解体する際の主な費用項目
| 費用項目 | 相場(目安) |
|---|---|
| 工具・機材の購入・レンタル | 5万~20万円 |
| 廃材の処分費(一般廃棄物・産業廃棄物) | 10万~50万円 |
| 人件費(応援を頼む場合) | 0~10万円 |
| 許可申請費用(建設リサイクル法・道路使用許可など) | 1万~5万円 |
| ライフライン撤去費(電気・ガス・水道) | 5千円~3万円 |
| その他(粉じん・騒音対策、養生シートなど) | 1万~3万円 |
| 合計 | 20万~80万円程度 |
💡 業者に依頼する場合の解体費用(30坪の木造住宅):80万~150万円
費用項目の詳細解説
1. 工具・機材の購入・レンタル(5万~20万円)
自分で解体するには、ハンマー・バール・チェーンソー・電動工具などが必要です。
【必要な道具と費用目安】
- ハンマー・バール(5,000円~1万円)
- 電動ノコギリ・グラインダー(2万~5万円)
- 粉じん対策のマスク・ゴーグル(5,000円~1万円)
- 脚立・はしご(1万円~3万円)
2. 廃材の処分費(10万~50万円)
解体で発生した木材・金属・コンクリート・断熱材・ガラスなどの廃棄物は、自治体のルールに従って適切に処分する必要があります。
【処分費の目安】
- 木材・プラスチック系廃材:10,000円~30,000円/㎥
- コンクリート・ガラ類:5,000円~15,000円/㎥
- 石膏ボード・断熱材:15,000円~25,000円/㎥
- 金属くず(リサイクル可能):無料~買い取り可能
3. 人件費(0~10万円)
自力で解体する場合、家族や友人の協力を得れば人件費はゼロですが、大きな作業が必要な場合はアルバイトや作業員を雇う選択肢もあります。
【費用目安】
- 作業員の日当:1万円~2万円/人
4. 許可申請費用(1万~5万円)
解体には、法律に基づく各種申請が必要です。特に、床面積80㎡以上の建物を解体する場合は、建設リサイクル法の届出が必須です。
【主な申請費用】
- 建設リサイクル法の届出(無料)
- 道路使用許可(1,000円~5,000円)
- 産業廃棄物処理の手数料(1万円~3万円)
5. ライフライン撤去費(5千円~3万円)
電気・ガス・水道の停止・撤去には、事前に各事業者への依頼が必要です。
【撤去費用の目安】
- 電気の撤去(メーター取り外し):無料~5,000円
- ガスの閉栓(メーター撤去含む):5,000円~20,000円(都市ガスかプロパンかで異なる)
- 水道の停止:無料~数千円
6. その他(粉じん・騒音対策、養生シートなど)
近隣住民への影響を抑えるため、防音シートや粉じん対策の水撒き設備の準備も必要です。
【その他の費用】
- 養生シート(防音・防塵用):1万円~3万円
- 散水ホース・ポンプ:5,000円~1万円
家を自分で解体するメリット・デメリット
家を自分で解体することには、費用の節約や自由度の高さといったメリットがある一方で、大きな手間やリスクを伴うデメリットもあります。それぞれのポイントを詳しく解説します。
メリット
費用を抑えられる(業者依頼より30~50%削減可能)
業者に依頼すると解体費用は80万~300万円程度かかりますが、自分で解体すればその30~50%を節約できる可能性があります。特に小規模な建物(10坪未満)の場合、業者の人件費や管理費をカットできるため、コストを大幅に削減できます。
工程を自分で管理できる(スケジュール調整が自由)
解体工事を自分で進めることで、作業のペースを自分で決められます。業者に頼むと日程が限られることが多いですが、自分で行えば都合の良い時間に少しずつ作業を進めることが可能です。特に急いでいない場合や、時間に余裕がある場合は、自分のペースで解体できるのは大きなメリットです。
デメリット
1.時間と手間がかかる
解体作業は想像以上に時間と労力を要します。特に手作業で進める場合、数週間~数ヶ月かかることもあります。
さらに、騒音や粉じんが発生するため、近隣への配慮も必要です。業者であれば事前に近隣住民へ説明をしてくれますが、自分で解体する場合は挨拶や説明を自分で行う必要があるため、トラブルにならないよう注意しましょう。
2. 危険が伴う(崩落・アスベスト・ケガのリスク)
家の解体には重たい建材や鋭利な工具を扱う作業が含まれるため、危険が伴います。特に以下のリスクがあります。
- 崩落の危険 → 壁や屋根を無計画に壊すと、思わぬ方向に倒壊するリスクがある
- 粉じん・アスベスト → 1970~1990年代に建てられた家にはアスベストが含まれる可能性がある
- 工具によるケガ → 電動工具の扱いに不慣れだと、手を切る・釘を踏むなどの事故が起こりやすい
3. 申請・法律を守る必要あり(違法解体のリスク)
家の解体には、建築リサイクル法や廃棄物処理法などの法的手続きが関わってきます。もしこれらの手続きを怠ると、罰則が科せられる可能性があるため、事前に確認しておく必要があります。
- 建設リサイクル法の届出(床面積80㎡以上の場合、自治体へ届出が必要)
- 産業廃棄物の適正処理(無許可の場所へ廃棄すると違法)
- 道路使用許可(道路にトラックを停める場合、警察の許可が必要)
家の解体を全て自分で行う方法もありますが「解体は業者に依頼し、残置物や家電製品の片付けは自分で行う」という選択肢もあります。
この方法では、専門的な技術やリスクを伴う解体作業は業者に任せつつ、残置物の片付けを自分で行うことで、解体費用を削減することができます。
例えば、以下のようなものは自分で片づけることが可能です
- 不要な家電製品
- 雑誌や書類
- 食材や調味料
- 玩具や食器類

家を自分で解体工事を行う際の注意点

処分場選びに注意
解体後に出る廃材は通常、産業廃棄物として扱われます。しかし、自分で解体工事を行う場合、廃材が「一般廃棄物」として分類される可能性もあります。一般廃棄物の場合、行政のリサイクルセンターで引き取ってもらえることがありますが、行政によって解釈が異なることがあるため、事前に窓口で確認することが大切です。
万が一、廃材が産業廃棄物として扱われる場合には、産業廃棄物処理業者に依頼して処分をお願いしなければなりません。この際、処分業者が不法投棄を行った場合、廃棄物を出した責任者が罰せられる可能性があるので、信頼できる業者を選ぶことが重要です。業者選定時には、許可を保有しているか、過去に違反歴がないかをしっかりと確認しましょう。
自己責任で進める覚悟を
解体工事を自分で行う場合、最も重要なのは「万が一のトラブルに対して全て自己責任で対応できるか」をよく考えることです。例えば、不法投棄、工事中の事故、近隣からの苦情など、さまざまなリスクがあります。そのため、解体作業を進める前に、自分が全てのリスクに責任を持てるかどうかを慎重に検討しましょう。
アスベスト除去は専門業者に依頼
アスベストは非常に危険で、飛散性があるため、除去作業を自分で行うことは健康に重大な影響を及ぼす可能性があります。アスベスト除去作業は、防護服を着用した専門技術者によって行われるべきです。もしアスベストが含まれていることが分かった場合、自分で除去作業をするのではなく、必ず専門のアスベスト除去業者に依頼しましょう。
まとめ
家を自分で解体することは可能ですが、いくつかの重要なポイントを理解し、準備を整える必要があります。家を解体する際には、計画的に進めることが重要です。しっかりと準備を行い、必要な申請手続きや廃材処理を遵守することで、安全かつスムーズに作業を進めることができます。解体後の手続きや近隣住民への配慮も忘れずに行い、トラブルなく工事を完了させることが成功のカギとなります。

都道府県別に解体工事会社と解体費用相場を見る
-
北海道・東北
-
関東
-
甲信越・北陸
-
東海
-
関西
-
中国
-
四国
-
九州・沖縄




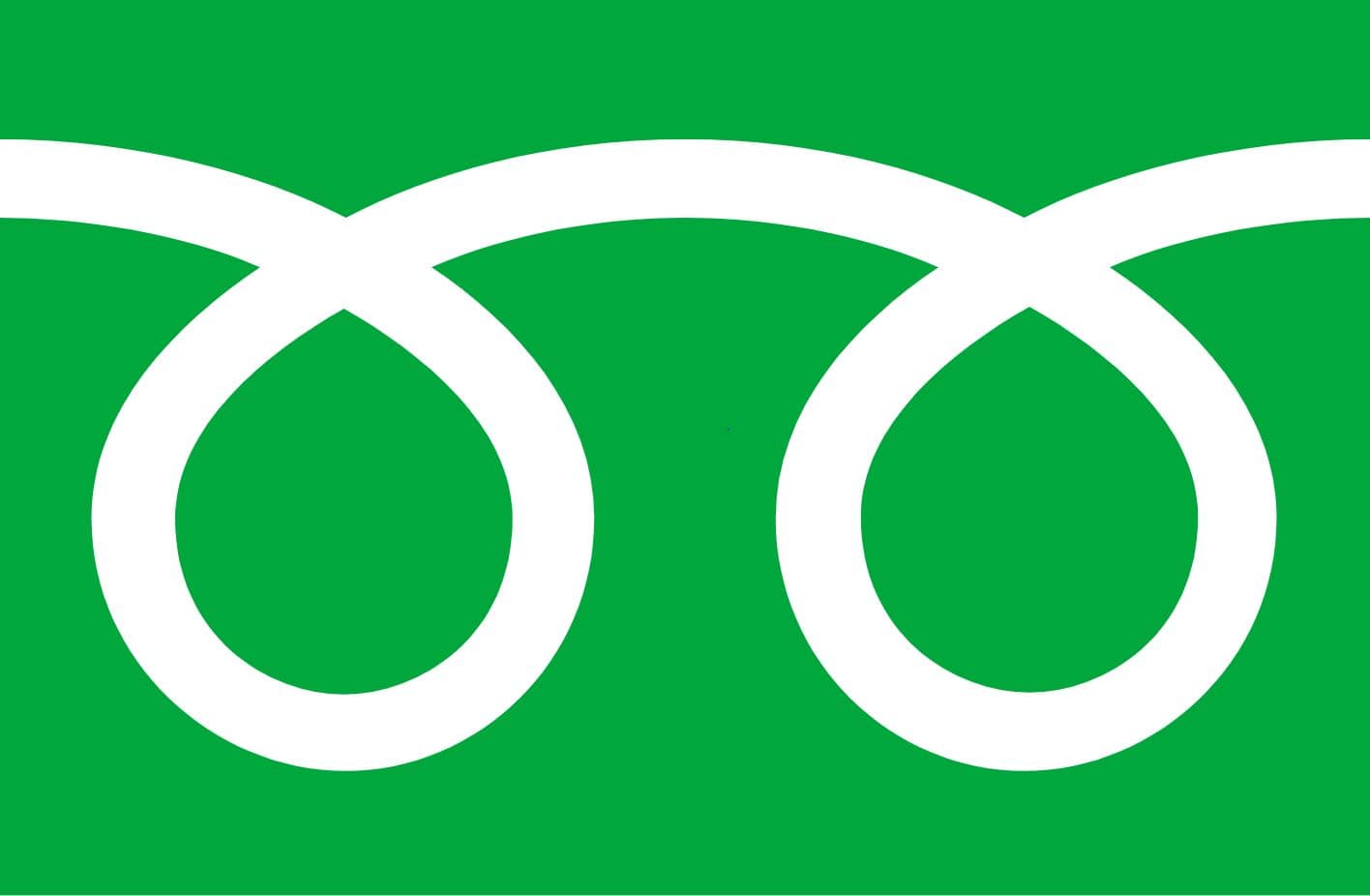 0120-479-033
0120-479-033