解体工事の工期・スケジュールはどのように進むのでしょうか?
家の建て替えを検討しています。解体工事と新築工事のスケジュールを考えていますが、できるだけ無駄な日が出ないよう、解体工事が終わってすぐに新築工事に入りたいと考えています。一般的な住宅のおおまかな作業内容と工期を教えてください。
一般的な解体工事のスケジュール
建物の状況により異なりますが、30坪の木造住宅を解体する場合のスケジュール例を示します。
解体期間は約7~10日間です。ただし、実際の工期は天候や作業条件によって変動する可能性があります。スムーズに進めるためには、業者と事前にしっかりと計画を立てておくことをおすすめします。

最終確認
工事範囲を施主立ち会いで確認し、必要に応じてマーキングを行います
近隣あいさつ
工事内容を説明し協力を依頼します。粗品やスケジュール表を持参すると良いでしょう
外構の解体(1日)
門や塀などを撤去し、重機が入れるスペースを確保します。
養生の設置(1日)
粉じんや破片の飛散を防ぐため、養生シートや防音シートを設置します。
建物の解体(約5日)
- 瓦・ガラス・内装材の撤去(2~3日)
- 構造体・基礎の解体(2~3日)
仕上げ作業(1日)
- 細かい破片の除去
- 地面の整地と清掃
完了確認と最終あいさつ
仕上がりを確認後、近隣へのお礼とお詫びを行います。

工事条件による影響
建物の材質
鉄骨や鉄筋コンクリート(RC)構造の場合、解体期間が木造の2倍程度になることがあります。
建物の大きさ
建物が大きいほど、解体期間が長くなります。
作業スペース
道路幅が狭い場合や敷地内のスペースが限られる場合、人力作業が増え、工期が延びることがあります。
マンション・ビル
大規模な建物では、事前調査(近隣住宅の傾き確認など)を行うため、余分な期間が必要です。
スケジュール表の発行は優良業者の基本

優良な解体業者であれば、工事の範囲や費用とともに、スケジュールを明確に提示するのが基本です。特に工事の開始日や終了日は、施主にとって非常に重要な要素となります。そのため、工事説明の際にスケジュール表を作成し、書面で発行するのは業者の責務ともいえます。
こうした対応をしっかり行う業者は、施主への説明やサポートを大切にしている証拠です。
書面発行を拒む業者には注意
一方で、業界全体ではサービスの質にばらつきがあり、口頭のみで概算のスケジュールを伝え、書面を発行しない業者も存在します。このような対応はトラブルの原因となる可能性が高いです。スケジュール表の発行タイミングは、見積り時点でなくても問題ありませんが、施主からの希望があれば速やかに対応できる業者を選びましょう。迅速かつ誠実な対応ができるかどうかは、優良業者の基準の一つです。
トラブル予防のためにスケジュール表は必須
解体工事では、施主と業者の間で誤解や説明不足によるトラブルが発生しやすいです。「言った」「聞いてない」といった議論に発展すると、気分を害するばかりか、工事の進行にも影響します。
そのため、契約書に着工日や納期を明記するだけでなく、細かいスケジュール表も書面で提示してもらうのが理想です。これにより、双方が工事計画を共有し、スムーズに進行させることができます。
業者選定のポイントとして活用
複数の業者を比較する際に、スケジュール表を提出してもらえるかどうかを判断材料にするのも一つの方法です。スケジュール表を作成・提出する業者は、施主への説明や工事計画の透明性を重視していることがわかります。こうした姿勢は、信頼できる業者を見極めるうえでの大きなヒントとなります。
スケジュール表の提出を業者にお願いする際は、希望の完成日や工期の条件をしっかり伝えたうえで依頼するとスムーズです。安心して依頼できる業者を選び、理想の家づくりを進めましょう。

都道府県別に解体工事会社と解体費用相場を見る
-
北海道・東北
-
関東
-
甲信越・北陸
-
東海
-
関西
-
中国
-
四国
-
九州・沖縄




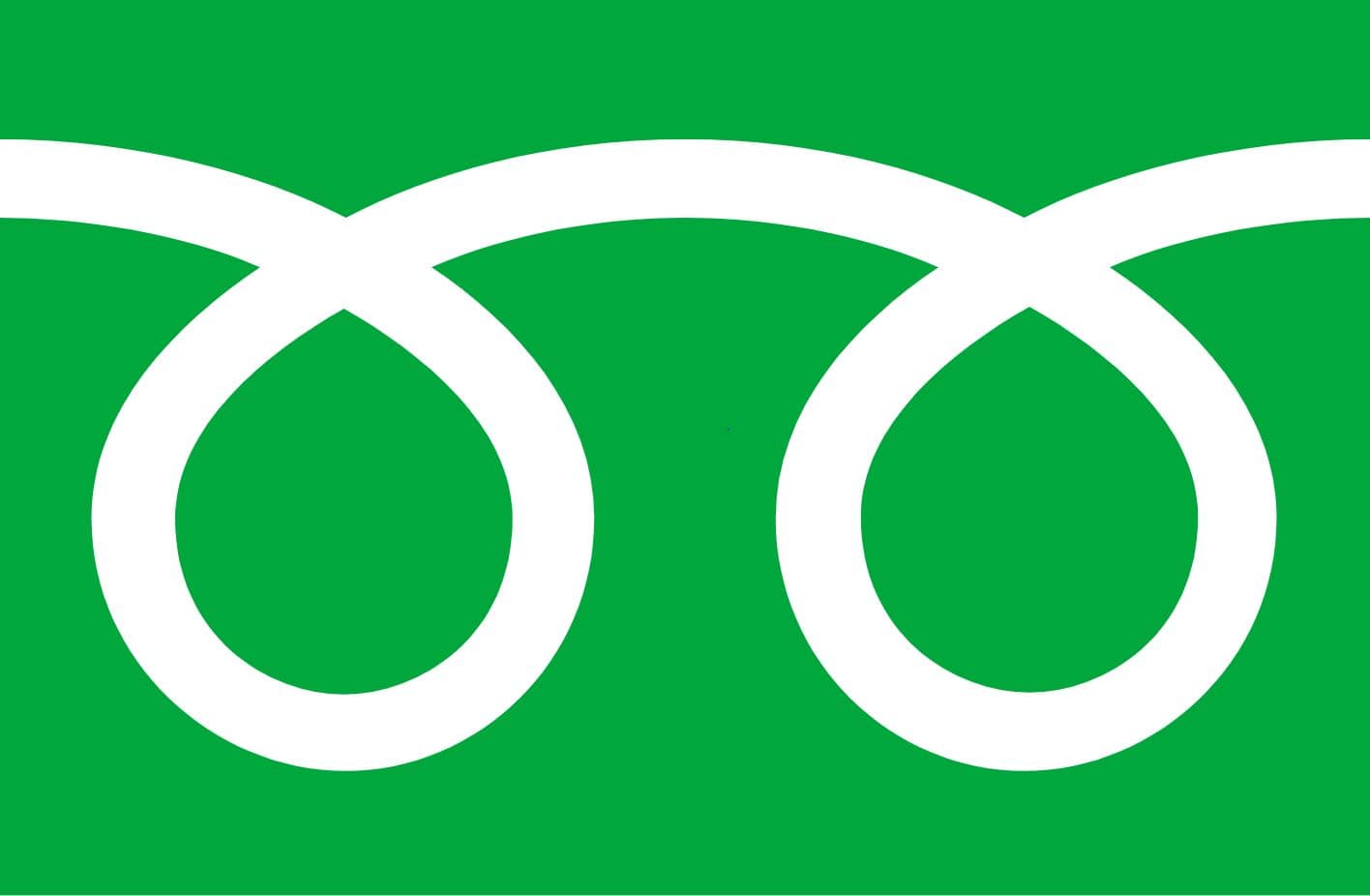 0120-479-033
0120-479-033