解体業の利益率は?意外と知らない利益率の実態と厳しい現実
「解体業は利益率が高いから、解体費用も高いのでは?」と考える方も多いかもしれません。しかし、解体費用が高くなる理由は、利益率だけではありません。解体工事には多くの要因が絡んでおり、工事の規模や地域、さらには法律や安全基準に基づくコストが大きな影響を与えています。
この記事では、解体業の利益率と解体費用の関係について詳しく説明し、解体費用がどのように算出されるのか、解説していきます。
解体業の利益率とは?その計算方法と業者間の違い
解体業者の利益率には業者ごとに差があり、利益率の計算方法についても理解しておくことが重要です。
利益率の計算方法
利益率は、(売上−コスト)÷売上 × 100という計算式で求められます。
例えば、解体工事の売上が200万円でコストが170万円かかった場合、利益率は15%となり、以下のように計算できます。
(売上200万円−コスト170万円)÷売上200万×100=利益率15%
売上が増えても、コストが増えれば利益率は低くなり、逆に売上が少なくてもコストを抑えれば、利益率は一定に保つことができます。このため、利益率を高く維持するためには効率的な運営とコスト管理が求められます。
解体業の利益率
解体業の利益率は、一般的に10%~20%の範囲に収まることが多いです。例えば、100万円の解体工事であれば、20万円が利益として残る計算です。また、一般財団法人建設業情報管理センターが発表した指標によると、建設業全体の売上高総利益率(粗利益率)は約20%弱であり、解体業もこの範囲に収まることが多いです。
業者によって異なる利益率
解体業者によって、利益率には差があります。工事の効率化やコスト削減に注力している業者は、比較的高い利益率を維持しています。一方で、経営や作業の効率に課題がある業者は、利益率が低くなることがあり、場合によっては粗利益が10%未満となることもあります。この差が生じる背景には、各業者の運営方針や施工体制が影響しています。
解体費用が高い=業者の利益率が高いわけではない
解体費用が高いからといって、必ずしもその業者の利益率が高いとは限りません。解体費用は、工事の規模や難易度、使用する設備や処分費用など、さまざまな要因によって決まります。そのため、費用が高い業者が必ずしも高い利益率を得ているわけではないのです。
なぜ解体費用は高くなるのか?
解体費用が高くなる背景には、いくつかの要因があります。ここでは、主な理由について詳しく解説します。
1. 重機や運搬費用
解体工事では、重機を使用して建物を解体します。このため、重機の購入やレンタル費用が必要となります。また、工事終了後の廃材や建物の破片を運搬する費用もかかります。これらの設備投資や運搬費用は工事の規模によって大きく変動し、高額になりやすいです。
2. 廃棄物処理費用
解体工事では、大量の廃材や産業廃棄物が発生します。これらを適切に処分するためには、廃棄物処理費用がかかります。また、廃材の分別や処理には時間と手間がかかり、それが解体費用を押し上げる要因となります。
3. 労働力のコスト
解体工事には高度な専門技術が必要で、経験豊富な作業員が求められます。このため、専門的なスキルを持つ作業員の人件費は一般的な作業より高額です。
4. 許認可・安全基準の遵守
解体工事は法的規制に基づいて行われます。近年、業界の安全基準が強化されており、業者はこれを遵守するために追加の費用がかかります。許可の取得や安全対策に必要なコストが、最終的な解体費用を高くする原因となります。

解体費用を抑える4つのポイント

家の解体費用に関する補助金制度
自治体によっては、補助金制度を活用できるケースがあります。以下のような内容の補助金制度を利用できる可能性があるため、解体したい建物がある場所の自治体制度を確認しましょう。
- 老朽危険家屋解体工事補助金
- 危険廃屋解体撤去補助金
- 木造住宅解体工事費補助時用
長期間使用されていない空き家があると、災害時に二次被害を引き起こす危険性があります。また、新しい建物が建てられないため、街の活性化が妨げられ、景観も損なわれてしまいます。そのため、長期間管理されていない住宅や耐震性の低い住宅の解体に対して、補助金が用意されていることが多いです
補助金については、自治体に直接確認するのも良いですが、解体業者にどのような補助金が利用できるか尋ねるのも一つの方法です。過去にその補助金を利用した経験のある業者であれば、具体的な条件や手続きについて詳しくアドバイスをもらえる可能性が高いでしょう
家の解体費用で受けられる補助金については、以下の記事でくわしく解説しています。
家の解体費用補助についてはこちら
残置物(家具・家電・日用品など)を自分で撤去して解体費用を安くする
家の中に残っている家具や家電、日用品などの残置物は、建物の解体で出る木くずやコンクリートガラとは異なる方法で処分する必要があるため、追加費用が発生するのが一般的です。そのため、解体費用を抑えたい方は、残置物を自分で処分することをおすすめします。
家具・家電・などの粗大ごみは、
- 自身でリサイクルセンターに持っていく
- 自治体に回収してもらう
日用品や骨董品などは、
- ジモティーやメルカリに出品し、リユースする
- 不燃ごみとして出す
等の方法があります。
自治体に粗大ごみや不燃ごみの回収を依頼する際は、「○○市 粗大ごみ」などと検索すると、関連する情報が掲載された自治体のホームページが見つかります。粗大ごみの回収には数百円から数千円程度の費用がかかりますが、解体業者に頼むよりもかなり安く済むでしょう。
必ず相見積もりを取ろう
解体業者に見積もりを依頼する際は、必ず相見積もりを取ることをおすすめします。同じ工事内容であっても、業者によって解体費用は異なるためです。
この差は、業者ごとの利益率の違いだけでなく、業者の拠点から現地までの距離や、他の仕事の状況によっても影響されます。たとえば、業者が他の案件で忙しいときは費用が高くなることがありますし、逆に時間に余裕があるときは割安で依頼できる場合もあります。このため、複数の業者からの見積もりを比較することが重要です。
解体工事会社(解体業者)の都合に合わせて工事を依頼しよう
解体工事会社(解体業者)は、お客様から「契約をしたいです」と言われた順に解体のスケジュールを抑えていきます。そのため「〇月〇日までに完工したい」と思っても、他のお客様のスケジュールによっては、金額が高くなる・解体の依頼ができないという事が起きます。
もし解体の期限に余裕がある場合は、工期を2か月程度設定し、「解体工事会社の手が空いているときに工事を行ってもらえますか?その分、少し割引してもらえませんか?」と値引き交渉をすることが可能です。
※一般的に、一軒家の解体には約2週間かかります。
特定の日にちまでに終わらせたいという場合は、お客様の都合に合わせたスケジュールを組む必要がありますが、工期を2か月や3か月と長めに取ることで、「○○市で工事があるから、そのついでに一緒に作業しよう」と他の工事と組み合わせてスケジュールを自由に調整できるためです。
解体費用が安すぎる業者のリスク
解体費用が安すぎる業者は注意が必要です。安価な料金を提供するために、安全基準を守らずに作業を行ったり、不法投棄をしたりする業者も存在します。このような業者は法的なトラブルを引き起こす可能性が高いため、選定時には慎重な判断が求められます。
解体業者を選ぶ際に、ただ単に「他社が利益率10%で見積もりを作っているので、御社も同じようにしてください」といった交渉は現実的ではありません。
重要なのは、担当者の対応、会社の姿勢、そして工事の品質と金額のバランスが取れているかどうかです。これらの要素をしっかりと検討することで、信頼できる業者を選定できます。
まとめ
解体業の利益率について理解することは、解体費用を適正に抑え、信頼できる業者を選ぶための重要なステップです。まず、解体業の利益率がどのように計算され、業者ごとにどんな違いがあるのかを知ることが、予算に対して適切な工事費用を見積もるうえでの基盤となります。高い解体費用が必ずしも高い利益率に直結するわけではないことも理解し、コスト削減方法を取り入れれば、より費用対効果の高い選択ができます。
しかし、解体費用が安すぎる業者にはリスクが伴うため、価格だけに注目せず、業者の信頼性や過去の実績をしっかりと確認することが大切です。解体費用を抑えるためには、複数の業者から相見積もりを取ったり、適切なタイミングで依頼したりすることが効果的です。
最終的には、工事の品質と金額のバランスを考慮した業者選びが、満足のいく解体工事を実現するカギとなります。

都道府県別に解体工事会社と解体費用相場を見る
-
北海道・東北
-
関東
-
甲信越・北陸
-
東海
-
関西
-
中国
-
四国
-
九州・沖縄





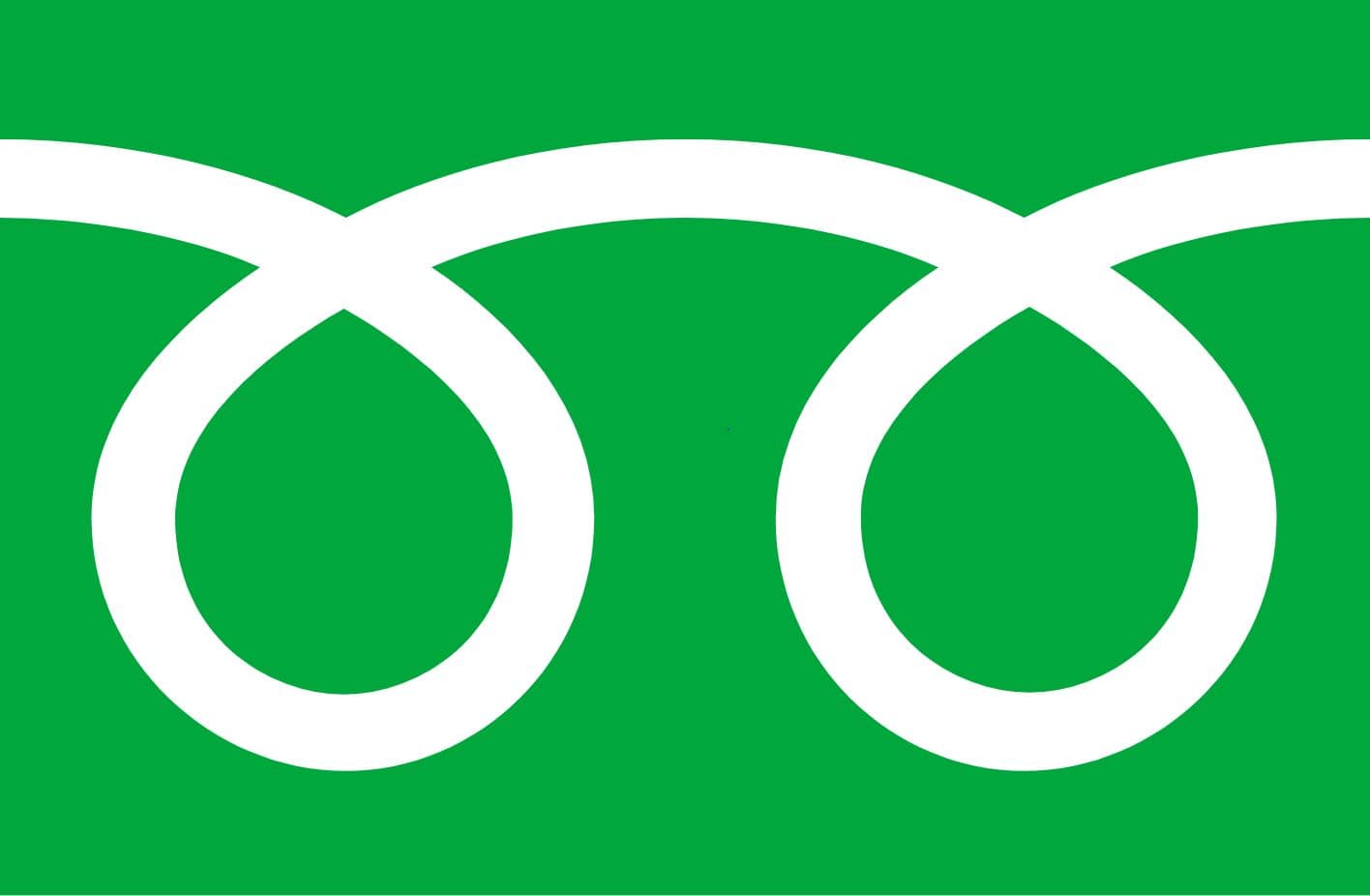 0120-479-033
0120-479-033