借地の建物解体は義務?費用負担のポイントと注意点を徹底解説!
借地に建てた建物を解体しようと考えたとき、「解体義務はあるのか?」「地主の承諾は必要?」「費用は誰が負担する?」 などの疑問が出てくるでしょう。正しい知識がないと、トラブルにつながる可能性があります。
本記事では、借地権の仕組みや解体義務の有無、解体費用の負担者、注意点などを詳しく解説します。
1. 借地とは?

「借地」とは、人から借りている土地のことを指します。
また、その土地を借りて家を建てる際に得る権利を「借地権」といいます。
土地の所有者は「地主(じぬし)」と呼ばれます。
地主が貸し出している土地は「底地」といい、その所有権を「底地権」といいます。
「借地」と「底地」は同じ土地を指しますが、呼び方は立場によって異なります。土地を借りる側は「借地」、貸す側は「底地」と呼びます。
借地権には、地上権と賃借権があり、目的や契約内容に違いがあります。
- 地上権
地上権は、土地に建物を建てることができ、長期間(土地利用の期間が数十年から永続的)にわたって土地を使用できる権利です。譲渡や相続も可能で、土地を自由に利用できる強い権利です。 - 賃借権
賃借権は、土地を借りるための権利で、契約期間は通常短期間(数年程度)です。建物を建てることができない場合があり、契約更新や解約が可能で、譲渡や相続に制限があります。
旧借地法と新借地法(新借地借家法)の違い
現在の借地権には「旧借地法」と「新借地借家法(平成4年8月施行)」の2つがあり、契約時期によって適用される法律が異なります。
旧借地法は、借地人(借りる側)の権利を強く守る仕組みでしたが、その影響で地主側とのトラブルが増え、借地の取引自体が減少する問題がありました。そこで、借地人と地主双方のバランスをとるために、新借地借家法が制定されました。
ただし、旧借地法の契約が自動的に新法へ移行することはなく、変更には新たな契約が必要です。そのため、自分の契約がどちらの法律に基づいているのか、契約書を確認することが重要です。
また、新借地借家法では「一般定期借地権」「事業用定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」などの制度があり、契約内容によっては借地上の建物の解体義務が発生することもあります。
自分の借地権はどちらに当てはまる?
借地権が「旧借地法」か「新借地借家法」かは、契約した時期によって決まります。
- 平成4年7月以前に契約 → 旧借地借家法が適用
- 平成4年8月以降に契約 → 新借地借家法が適用
旧借地法で契約した場合、更新しても新借地借家法に自動的に切り替わることはありませんそのため、自分の契約がどの法律に基づいているのかを、契約書を確認して把握しておくことが大切です。

借地上の建物の解体は可能?
借地に建物を所有している場合、借主の判断だけで解体できるのか疑問に思うかもしれません。
結論として、借地上の建物は解体できます。ただし、地主の承諾が必要となるため注意が必要です。
借地権付き建物の解体費用は、通常、借地権者(建物の所有者)が負担します。借地人には、契約終了時に建物を撤去し、原状回復する義務があるのが一般的です。特に契約書に「契約終了時に更地で返還する」と明記されている場合、借主が負担するのは義務となります。
※建物を解体しても、原則として借地権が消滅することはありません<。これは旧借地借家法でも新借地借家法でも同様です。
借地上の建物の解体費用相場
借地上の建物の解体費用は、建物の構造によっておおよその相場が異なります。以下のように参考にできます。
- 木造:3~4万円/坪
木造住宅の解体費用相場についてはこちら - 鉄骨造:4~6万円/坪
鉄骨造住宅の解体費用相場についてはこちら - RC造(鉄筋コンクリート造):5~8万円/坪
RC住宅の解体費用相場についてはこちら
カーポートやブロック塀など外構も解体する必要がある場合や、アスベストの除去が必要なケースなど、別途費用が必要になります。
| 家の構造 |  木造 |  鉄骨造 |  鉄筋コンクリート造 |
| 10坪 | 31〜44万円 | 34〜47万円 | 35〜80万円 |
| 20坪 | 62〜88万円 | 68〜94万円 | 70〜160万円 |
| 30坪 | 93〜132万円 | 102〜141万円 | 105〜240万円 |
| 40坪 | 124〜176万円 | 136〜188万円 | 140〜320万円 |
| 50坪 | 155〜220万円 | 170〜235万円 | 175〜400万円 |
| 60坪 | 186〜264万円 | 204〜282万円 | 210〜480万円 |
| 70坪 | 217〜308万円 | 238〜329万円 | 245〜560万円 |
| 80坪 | 248〜352万円 | 272〜376万円 | 280〜640万円 |
| 90坪 | 279〜396万円 | 306〜423万円 | 315〜720万円 |
| 100坪 | 310〜440万円 | 340〜470万円 | 350〜800万円 |
解体業者選びのポイント!信頼できる業者の見分け方と選び方
解体業者を選ぶうえでのポイントを5つご紹介します。
①過去の行政処分や指名停止歴をチェック
解体工事は大規模で危険を伴う作業が多いため、法律を遵守し、適正に運営されている業者を選ぶことが重要です。過去に行政処分や指名停止を受けた業者は、法令違反やトラブルを起こした可能性があり、依頼する際のリスクが高まります。
【行政処分や指名停止の主な理由】
- 産業廃棄物の不法投棄(適切な廃棄処理を行わず、違法に処分)
- 無許可での営業(建設業許可・解体工事業登録なしでの工事)
- 安全管理の不備(適切な責任者が不在で、作業員や近隣住民に危険を及ぼす)
- 違法な契約・不正な見積もり(契約違反や不透明な追加請求)
各自治体の公式サイトや国土交通省の指名停止業者リストを確認する
「○○会社 行政処分」や「○○解体 指名停止」と検索
②施工実績
施工実績は、解体工事会社を選ぶうえで重要な判断基準のひとつです。過去にどのような建物の解体を手がけたかを確認することで、技術力や対応できる工事の規模を把握できます。特に、自宅や所有物件と同じような建物の解体経験が豊富な会社であれば、安心して依頼しやすくなります。
また、施工事例が写真付きで掲載されている場合は、工事の丁寧さや仕上がりの質もチェックできます。さらに、自治体や企業などからの依頼実績がある場合は、信頼性の高い業者である可能性が高いでしょう。
③許可の有無
解体工事を安全かつ適切に行うためには、必要な許可を取得していることが欠かせません。特に解体工事業登録や建設業許可を持っているかを確認しましょう。これらの免許は、一定の技術力や法令遵守の基準を満たしている証です。
無免許の業者に依頼すると、法令違反のリスクだけでなく、近隣トラブルや工事の質の低下につながる可能性があります。安心して任せるためにも、事前に免許の有無をしっかり確認し、信頼できる業者を選びましょう。
④見積りの重要性
解体工事の見積もりを比べる際、総額だけに目が行きがちですが、実際には「何にどれくらいの費用が使われているのか」をしっかり確認することが大切です。見積もり内容が詳細に記載されている業者の方が、料金の内訳が分かりやすく比較もしやすいため、おすすめです。
また、見積もりを取る際は、必ず複数の業者から取ることをお勧めします。見積もりには、工事費用だけでなく、作業内容や工期、追加費用の有無なども明記されていることが重要です。これを確認することで、料金が明確になり、予算オーバーを避けることができます。
⑤対応の丁寧さ
業者の担当者が親身になって質問に答えてくれるか、説明が分かりやすく丁寧かどうかをチェックしましょう。疑問点があればすぐに解決できるか、こちらの不安をしっかりと理解し、安心感を与えてくれる業者は信頼できます。
また、迅速で正確な返信をしてくれる業者は、仕事も丁寧に進めてくれる可能性が高いです。見積もり依頼や質問に対するレスポンスの速さ、電話やメールでの対応がスムーズかどうかを確認することが大切です。
借地権の建物を解体しなくてよいケースと解体を回避する方法
借地上の建物を解体しなくても済む方法はいくつかあります。契約内容や地主との交渉次第で、借地人が解体費用を負担しなくて済む場合もあります。ここでは、借地における建物の解体義務を回避するための具体的な方法 を解説します。
解体不要または地主が負担するケース
借地契約の内容によっては、建物の解体義務が借地人に発生しないことがあります。以下のケースに該当する場合は、解体費用を支払わずに済む可能性があります。
- 契約書に「更地で返還」と明記されていない
- 借地契約書に「契約終了時は更地で返還する」との記載がない場合、建物の解体義務は発生しません。
- ただし、実際には地主との交渉次第となるため、契約終了時に建物をどう扱うか、事前に確認しておくことが重要です。
- 契約書に「解体費用は地主負担」と明記されている
- 契約書に「解体費用は地主が負担する」と明記されている場合、地主が解体費用を支払う義務を負います。
- 契約書の内容を確認し、必要に応じて専門家に相談しましょう。
建物を解体せずに済む方法
解体義務を回避するためには、以下のような方法が考えられます。
- 建物買取請求権を行使する
- 借地人には「建物買取請求権」という権利があり、地主に建物を買い取らせることができます。
- これにより、借地人が建物を解体せずに済むケースがあります。
- ただし、この権利を行使するには契約期間満了時であることや、借地人が契約違反をしていないことなどの条件を満たす必要があります。
- 借地権を第三者に売却する
- 借地権は第三者に売却できますが、通常は地主の承諾が必要です。
- また、地主の承諾を得るために「譲渡承諾料」が必要となるケースもあります。一般的に更地価格の10%程度が目安とされています。
- 借地権の売却を検討する場合は、借地権売買を専門に扱う不動産会社に相談するとスムーズです。
- 借地権を地主に買い取ってもらう
- 借地権は不動産としての価値があり、地主に買い取ってもらうことが可能です。
- 特に地主が土地を自ら活用したいと考えている場合、交渉が成立しやすくなります。
- 借地権の買取価格は一般的に更地価格の50%程度とされていますが、地域や契約内容によって異なるため、事前に価格相場を調査することが重要です。
- 建物を地主に無償譲渡する
- 建物を地主に無償で譲渡することで、解体費用を負担せずに済む場合があります。
- ただし、地主がこれを受け入れるかどうかは交渉次第であり、地主が建物の活用方法を持っていない場合は拒否されることもあります。
まとめ
借地上の建物の解体についてお伝えしました。
借地上の建物を借地人が解体することは可能ですが、解体前に地主の承諾を受ける必要があったり、契約書に記載がある場合には指定の解体業者を使う必要があったりなど、気を付けなければならない点もあります。
将来的に活用する見込みがないケースで、借地上の建物の解体を検討されている場合には、本記事の内容を参考に手続きを進めるようにしましょう。

都道府県別に解体工事会社と解体費用相場を見る
-
北海道・東北
-
関東
-
甲信越・北陸
-
東海
-
関西
-
中国
-
四国
-
九州・沖縄





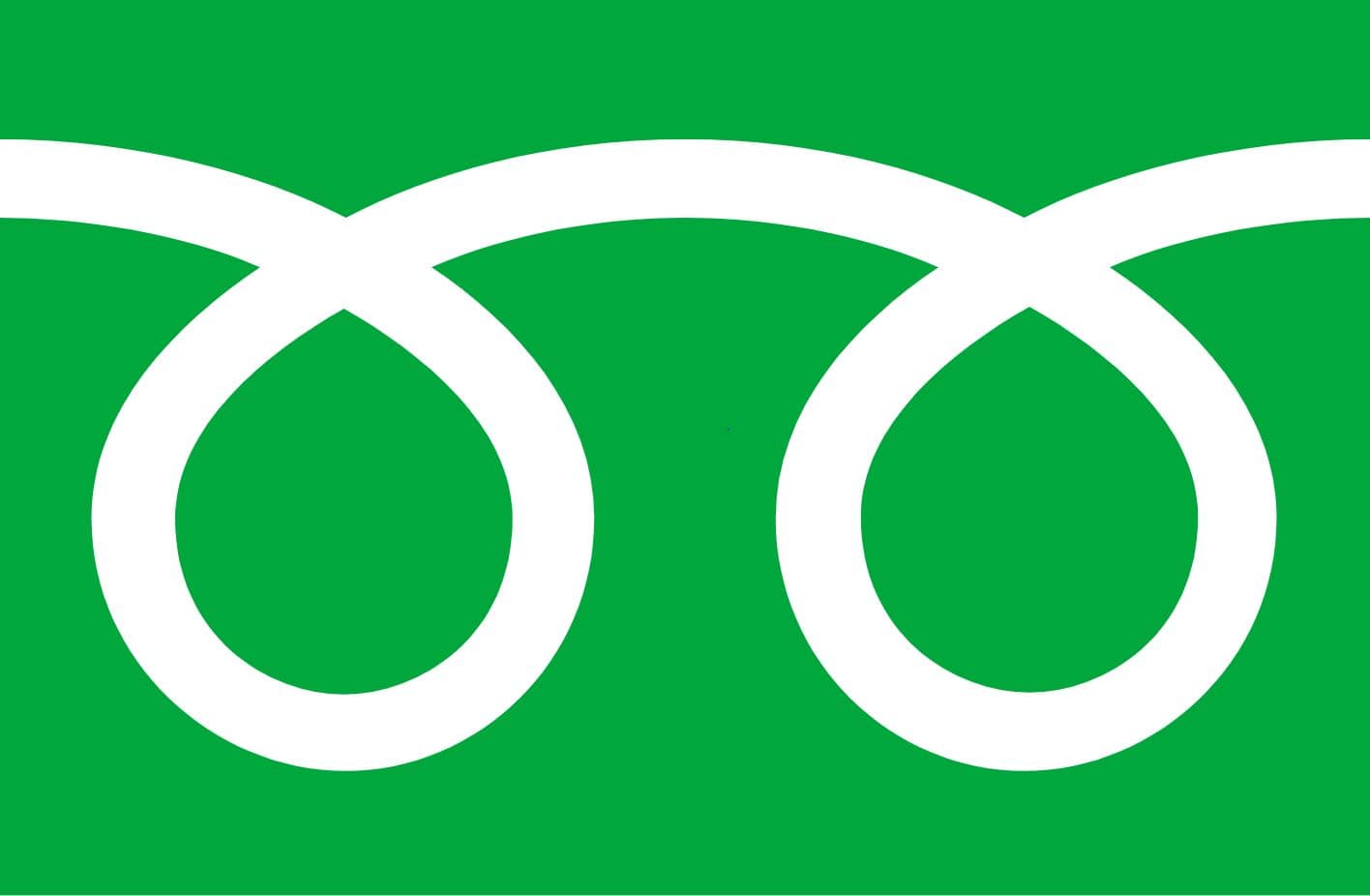 0120-479-033
0120-479-033